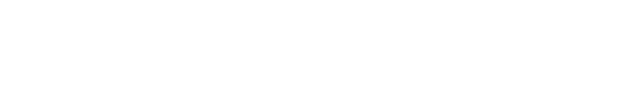においがしない
「あれ、今日のご飯、なんだか味がしないな…」と感じたことはありませんか? 実は、味覚は嗅覚と密接に関わっており、「におい」がしないと、食べ物の味がわかりにくくなるだけでなく、生活の安全にも影響を及ぼすことがあります。
においを感じる仕組み
私たちがにおいを感じるためには、以下のステップが必要です。
- におい分子の吸入:空気中に漂うにおい分子が、鼻の穴から吸い込まれます。
- 嗅裂への到達:吸い込まれたにおい分子は、鼻の奥にある「嗅裂(きゅうれつ)」と呼ばれる場所に到達します。
- 補足:嗅裂は、鼻の最上部にある狭い空間です。
- 嗅上皮の刺激:嗅裂には、においを感じるための「嗅上皮(きゅうじょうひ)」という粘膜があり、この中に「嗅細胞(きゅうさいぼう)」と呼ばれる神経細胞があります。におい分子が嗅細胞に到達すると、嗅細胞が刺激されます。
- 脳への信号伝達:刺激された嗅細胞は、電気信号を脳に送ります。
- においの認知:脳で電気信号が処理され、私たちはにおいを認識します。
においがしなくなる原因
においを感じる過程のどこかに異常があると、においがしなくなったり、においの感じ方が変わったりします。主な原因としては、以下のものがあげられます。
1.におい分子が嗅上皮に届かない場合
鼻の病気
- 風邪(急性鼻炎): ウイルス感染によって鼻の粘膜が腫れ、嗅裂が狭くなると、におい分子が嗅上皮に届きにくくなります。
- アレルギー性鼻炎:アレルギー物質によって鼻の粘膜が炎症を起こし、腫れることで、におい分子が嗅上皮に届きにくくなります。
- 慢性副鼻腔炎:副鼻腔(鼻の奥にある空洞)に炎症が慢性的に続くと、鼻の粘膜が腫れたり、鼻茸ができたりして、におい分子が嗅上皮に届きにくくなります。
- 鼻中隔弯曲症(びちゅうかくわんきょくしょう): 鼻の左右を分ける壁(鼻中隔)が曲がっていると、鼻の通りが悪くなり、におい分子が嗅上皮に届きにくくなります。
その他
- 補足:鼻ポリープ(鼻茸): 鼻の粘膜にできるポリープが大きくなると、鼻の通りを塞いでしまい、におい分子が嗅上皮に届きにくくなります。
2.嗅細胞自体がダメージを受けた場合
- ウイルス感染: 風邪のウイルスなどが嗅細胞自体を傷つけてしまうと、嗅覚が著しく低下することがあります。
- 神経系の病気: 脳腫瘍や神経変性疾患などが、嗅細胞や嗅神経に影響を与え、嗅覚障害を引き起こすことがあります。
- 頭部外傷: 頭部を強く打った際に、嗅神経が損傷し、嗅覚障害が起こることがあります。
- 薬の副作用: 一部の薬の副作用として、嗅覚障害が起こることがあります。
3.その他の原因
- 加齢:加齢に伴い、嗅細胞の機能が低下し、嗅覚が衰えることがあります。
- 栄養不足:ビタミンや亜鉛などの栄養不足が、嗅覚障害の原因となることがあります。
- 喫煙:喫煙は、嗅細胞を傷つけ、嗅覚を低下させる可能性があります。
- 化学物質:一部の化学物質に長期間さらされると、嗅覚障害が起こることがあります。
においがしないことによる影響
においがしないと、以下のような影響が出ることがあります。
- 味覚の低下:味を感じるには、においの情報が重要です。においがしなくなると、食べ物の味がわかりにくくなります。
- 食欲不振:食べ物の味がわからなくなると、食欲が低下することがあります。
- 食中毒のリスク:食品の腐敗臭に気づきにくくなり、食中毒を起こすリスクが高まります。
- ガス漏れなどの危険:ガス漏れなどの異臭に気づきにくくなり、危険を察知するのが遅れる可能性があります。
- 精神的な影響:香りを楽しめなくなることから、生活の質が低下し、うつ状態になることもあります。
においがしない場合の検査と診断
においがしない原因を特定するために、耳鼻咽喉科では以下のような検査を行います。
- 問診:いつからにおいがしなくなったか、きっかけとなるような出来事があったか、他の症状を伴うかなどを詳しくお聞きします。
- 鼻鏡検査:鼻の穴の中を観察し、鼻の粘膜の状態や鼻茸の有無などを確認します。
- レントゲン検査:必要に応じて、鼻や副鼻腔のレントゲン検査を行います。
- CT検査:より詳細な状態を確認するために、鼻や副鼻腔のCT検査を行うことがあります。
- 嗅覚検査:
- 静脈性嗅覚検査:においのついた薬を静脈注射し、どのくらいでにおいを感じるかを調べる検査です。
- T&Tオルファクトメトリー:複数種類のにおいを異なる濃度で嗅いでもらい、嗅覚の程度を判定する検査です。
- 血液検査:必要に応じて、血液検査を行い、炎症や栄養状態を確認します。
においがしない場合の治療法
においがしない場合の治療は、原因によって異なります。
1.鼻の病気が原因の場合
- 風邪やアレルギー性鼻炎:炎症を抑える薬(抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬など)を使用します。
- 慢性副鼻腔炎:抗菌薬やステロイド薬を使用し、炎症を抑えます。必要に応じて手術を行うこともあります。
- 鼻中隔弯曲症:手術で鼻中隔を矯正することがあります。
- 鼻ポリープ:手術でポリープを切除することがあります。
2.嗅細胞のダメージが原因の場合
- ステロイド薬:炎症を抑え、嗅細胞の回復を促すためにステロイド薬を内服したり、点鼻したりします。
- ビタミン剤:ビタミン不足が疑われる場合は、ビタミン剤を服用します。
- 亜鉛:亜鉛不足が疑われる場合は、亜鉛を補給します。
3.その他の原因の場合
- 禁煙:喫煙が原因の場合は、禁煙を勧めます。
- 化学物質の回避:化学物質が原因の場合は、原因物質を避けるようにします。
- 生活習慣の改善:バランスの取れた食事や十分な睡眠をとり、ストレスを溜めないようにしましょう。
4.共通の治療法
- 鼻洗浄:生理食塩水などで鼻を洗浄し、鼻の中を清潔に保ちます。
- ネブライザー療法:薬液を霧状にして鼻やのどに吸入させ、炎症を抑えます。
まとめ
においがしない、またはにおいの感じ方がおかしいと感じたら、放置せずに耳鼻咽喉科を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。早期に治療を開始することで、嗅覚の回復を促し、生活の質を改善することができます。
(お困りの際は、当院までご相談ください。適切な対応をさせていただきます。)