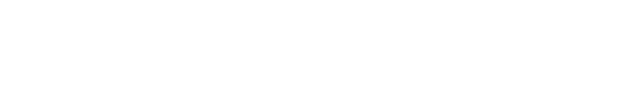めまい・ふらふらする
「ぐるぐると目が回る」「フワフワして足元が定まらない」など、めまいやふらつきの症状は、多くの方が経験する不快なものです。めまいは、日常生活に支障をきたすだけでなく、時には重篤な病気のサインである可能性もあります。ここでは、めまいやふらつきの原因、対処法について詳しく解説します。
めまいとは?
めまいとは、実際には自分や周囲が動いていないのに、動いているように感じる感覚を指します。めまいの種類や症状は様々ですが、大きく分けて以下の2つに分類できます。
- 回転性めまい:
- 特徴: 自分自身や周囲がグルグルと回っているように感じるめまい。
- 原因: 内耳(ないじ:耳の奥にあるバランスを司る器官)の異常が原因であることが多いです。
- 浮動性めまい(ふらつき):
- 特徴: 体がフワフワしたり、足元が定まらない感じがするめまい。
- 原因: 脳の異常、心臓や血管の病気、自律神経の乱れなど、様々な原因が考えられます。
めまいの原因
めまいの原因は多岐にわたりますが、主な原因として以下のものが挙げられます。
1.内耳(ないじ)性のめまい
- 良性発作性頭位めまい症(BPPV): 特定の頭の位置や動きによって、回転性のめまいが起こる病気。耳の中にある耳石(じせき)という小さな石が剥がれて、三半規管(さんはんきかん:バランスを司る器官)に入り込んでしまうことが原因と考えられています。
- メニエール病:内耳のリンパ液が過剰に溜まることで、回転性のめまい、難聴、耳鳴りなどの症状が繰り返し起こる病気。
- 前庭神経炎(ぜんていしんけいえん):内耳にある前庭神経が炎症を起こし、激しい回転性めまいや吐き気などの症状が起こる病気。
- 突発性難聴: 突然、片側の耳の聞こえが悪くなる病気。めまいを伴うこともあります。
- 外リンパ瘻(がいりんぱろう):内耳のリンパ液が漏れ出す病気で、めまいや難聴などの症状が現れることがあります。
- 内耳炎:内耳に炎症が起こることで、めまいや難聴を引き起こすことがあります。
2.中枢性のめまい
- 脳梗塞・脳出血: 脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の機能が障害され、めまいや吐き気、手足の麻痺などの症状が現れることがあります。
- 脳腫瘍:脳にできた腫瘍が、脳のバランス感覚を司る部分を圧迫することで、めまいを起こすことがあります。
- 椎骨脳底動脈循環不全(ついこつのうていどうみゃくじゅんかんふぜん):脳に血液を送る椎骨動脈や脳底動脈の血流が悪くなり、めまいやふらつき、吐き気などの症状が現れることがあります。
- 脳炎・髄膜炎:脳や脊髄を覆う膜に炎症が起こり、めまいや発熱、頭痛などの症状が現れることがあります。
- 片頭痛:頭痛に伴ってめまいが起こることがあります。
3.その他の原因
- 起立性低血圧:急に立ち上がったときに、血圧が低下し、ふらつきやめまいが起こる状態。
- 心臓の病気:不整脈や心不全などの心臓の病気が原因で、脳への血流が減少し、めまいを起こすことがあります。
- 貧血:血液中の酸素を運ぶ赤血球が不足すると、脳に酸素が十分に供給されなくなり、めまいやふらつきを起こすことがあります。
- 低血糖:血糖値が急激に低下すると、めまいやふらつき、動悸などの症状が現れることがあります。
- 自律神経失調症:自律神経のバランスが乱れることで、めまいやふらつき、動悸、発汗などの症状が現れることがあります。
- 更年期障害:更年期になるとホルモンバランスが乱れ、めまいやふらつきを感じることがあります。
- 薬の副作用:一部の薬の副作用として、めまいやふらつきが起こることがあります。
- ストレス:ストレスが溜まると、自律神経のバランスが乱れ、めまいやふらつきを引き起こすことがあります。
- 過労・睡眠不足:過労や睡眠不足は、めまいやふらつきの原因となることがあります。
めまいの検査と診断
めまいの原因を特定するために、耳鼻咽喉科や神経内科では、以下のような検査を行います。
- 問診:いつから症状が出始めたか、どのようなめまいか(回転性か浮動性か)、他に症状があるかなどを詳しくお聞きします。
- 眼振検査:目を動かしてもらい、眼球の動き(眼振)を観察します。眼振の有無や種類によって、めまいの原因を特定する手がかりになります。
- 聴力検査:耳の聞こえ具合を調べます。
- 平衡機能検査:バランス感覚を調べる検査を行います。
- 重心動揺計検査:立った時の体の揺れを測定します。
- 足踏み検査:目をつぶって足踏みをしてもらい、体の傾きを調べます。
- 温度刺激検査:耳の中に冷たい水や温かい水を注入し、めまいを誘発させ、眼振を観察する検査です。
- 神経学的検査:脳や神経の機能に異常がないか調べる検査を行います。
- 画像検査:必要に応じて、頭部のレントゲン検査、CT検査、MRI検査などを行い、脳や内耳に異常がないかを確認します。
- 血液検査:貧血や炎症の程度などを調べます。
- 心理検査:必要に応じて、心理的な要因がめまいの原因になっていないか調べるための心理検査を行います。
めまいの治療法
めまいの治療法は、原因によって異なります。
1.内耳性のめまいの場合
- 良性発作性頭位めまい症:めまいを誘発する体位をとることで、耳石を元の位置に戻す治療(エプリー法など)を行います。
- メニエール病:めまいを抑える薬や、利尿剤、内耳の循環を改善する薬などを使用します。
- 前庭神経炎:炎症を抑える薬や、吐き気止めなどを使用します。
- 突発性難聴: ステロイド薬などを使用します。
2.中枢性のめまいの場合
- 脳梗塞・脳出血:脳卒中の専門的な治療を行います。
- 脳腫瘍:手術や放射線治療などを行います。
- 椎骨脳底動脈循環不全:血流を改善する薬を使用します。
- 脳炎・髄膜炎:炎症を抑える薬を使用します。
- 片頭痛:頭痛を抑える薬を使用します。
3.その他の原因の場合
- 起立性低血圧:ゆっくりと立ち上がるように心がけ、必要に応じて血圧を上げる薬を使用します。
- 心臓の病気:心臓の専門医による適切な治療を行います。
- 貧血:鉄剤やビタミン剤を服用します。
- 低血糖:食事療法や生活習慣の改善を行います。
- 自律神経失調症:自律神経のバランスを整える薬や、カウンセリングなどを行います。
- 更年期障害:ホルモン補充療法を行うことがあります。
- 薬の副作用:医師と相談し、薬の調整や変更を検討します。
日常生活での注意点
- 無理をしない:めまいが起こった場合は、無理をせず安静にしましょう。
- ゆっくりと行動する:急な動作は、めまいを誘発することがあるため、ゆっくりと行動するように心がけましょう。
- 規則正しい生活を心がける:睡眠時間を確保し、バランスの取れた食事をとり、ストレスを溜めないように心がけましょう。
- アルコールやカフェインを控える:アルコールやカフェインは、めまいを悪化させることがあるため、控えましょう。
- 水分補給を心がける:脱水はめまいを引き起こす原因になるため、こまめに水分補給をしましょう。
- 周囲の環境に注意する:めまいが起こりやすい場合は、階段や高所など危険な場所を避けるようにしましょう。
まとめ
めまいやふらつきは、様々な原因で起こりうる症状です。放置すると日常生活に支障をきたしたり、重篤な病気が隠れている可能性もあります。症状が続く場合は、自己判断せずに早めに耳鼻咽喉科や神経内科を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。
(お困りの際は、当院までご相談ください。適切な対応をさせていただきます。)