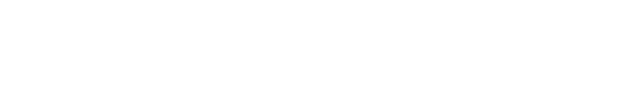喉頭炎
1.概要
喉頭炎(こうとうえん)とは、ウイルスや細菌、アレルギー、喫煙など、さまざまな原因で喉頭(声帯を含む部分)に炎症が生じた状態の総称です。急性と慢性に大きく分けられ、急性喉頭炎では主に声のかすれや発熱などが、慢性喉頭炎では声のかすれやせきといった症状が持続的にみられます。喉頭は空気の通り道でもあるため、炎症が強くなると呼吸が苦しくなることがあるため注意が必要です。
2.症状
- 急性喉頭炎:声のかれ(嗄声〈させい〉)、せき、のどの痛み、発熱などが中心。喉頭の腫れが強い場合は呼吸困難を伴うこともある。
- 慢性喉頭炎:長期間にわたる声のかれ、せきなどが主な症状。急性ほど強い痛みや発熱はないが、症状が長引く。
- その他:急性喉頭蓋炎や急性声門下喉頭炎など、短時間で呼吸困難を起こす重症タイプもあり、注意が必要。
3.原因
- ウイルス・細菌感染:風邪やインフルエンザウイルス、細菌などが喉頭に感染する。
- アレルギー:花粉症やハウスダストなどのアレルギー反応が喉頭炎を引き起こす場合がある。
- 喫煙・飲酒:タバコの煙やアルコールが喉頭を刺激し、炎症を起こしやすくする。
- 声の酷使:長時間の大声や不適切な発声方法で喉頭に負担をかける。
- その他:逆流性食道炎による胃酸の刺激、空気の乾燥なども喉頭炎の一因となることがある。
4.診断
- 問診・視診:症状の経過や喉の痛みの程度、声の状態などを詳しく確認。
- 喉頭内視鏡検査:鼻や口から内視鏡を挿入し、喉頭の赤みや腫れ、声帯の状態を直接観察する。
- 画像検査・血液検査:重症例や他の疾患の可能性を疑う場合、X線やCT、血液検査などを行い、炎症や感染症の有無を確認。
5.治療
- 急性喉頭炎
- 声や全身の安静を保ち、声帯への負担を減らす。
- 抗炎症薬や抗菌薬(細菌感染が疑われる場合)、吸入療法(ネブライザー)などを用いて炎症を抑える。
- 症状が強い場合や呼吸困難がある場合、入院して治療を行うことも。
- 慢性喉頭炎
- 原因となる刺激(喫煙、過度な飲酒、アレルギーなど)の除去に努める。
- 吸入療法や声のリハビリテーション(発声指導)など、局所治療を中心に行う。
- 喉頭結核など特別な病気が疑われる際には、専門的な治療が必要となる場合がある。
喉頭炎は悪化すると呼吸困難や声の問題につながり、生活の質を大きく左右する可能性があります。声がかすれたり、せきやのどの痛みが長引く場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。