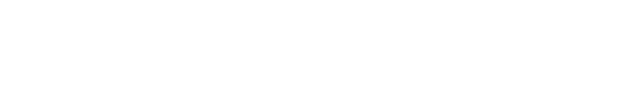耳がつまる
「耳に水が入ったような感じ」「耳がふさがれたような感じ」「ボワーンとした感じ」など、耳のつまり感は、多くの方が経験する不快な症状です。この症状は、耳のどの部分に原因があるかによって、さまざまなケースが考えられます。
耳の構造と耳のつまり感
耳は、外側から「外耳」「中耳」「内耳」の3つの部分に分けられます。
- 外耳:耳の穴から鼓膜までの部分。
- 中耳:鼓膜の奥にある空間。
- 内耳:音を感知する重要な器官。
耳のつまり感は、これらのどの部分に異常があっても起こる可能性があります。
耳のつまり感の原因
耳のつまり感の原因は、大きく分けて以下の3つに分類できます。
1.外耳の異常による耳のつまり感:
- 耳あか:耳あかが過剰に溜まったり、硬くなって耳の穴を塞いでしまうと、耳のつまり感や聞こえにくさを感じることがあります。
- 異物:綿棒の先や小さな虫などが耳の中に入り込んでしまうと、耳のつまり感や痛みを感じることがあります。
- 水:プールやお風呂で水が耳に入ると、一時的に耳のつまり感を感じることがあります。
- 外耳炎:外耳道の皮膚が炎症を起こし、腫れたり分泌物が溜まると、耳のつまり感や痛みを感じることがあります。
- サーファーズイヤー(外耳道骨腫): 海水や風にさらされることで外耳道の骨が過剰に増殖し、耳の穴が狭くなる状態。サーフィンをする人に多く見られます。耳の穴が狭くなると、耳あかが溜まりやすくなり、耳のつまり感を感じることがあります。
2.中耳の異常による耳のつまり感:
- 耳管狭窄症(じかんきょうさくしょう): 鼻の奥と中耳をつなぐ耳管が、風邪などで腫れてしまい、中耳の空気圧を調整する機能がうまく働かなくなると、耳のつまり感を感じることがあります。
- 補足: 耳管は、通常は閉じていますが、つばを飲み込んだり、あくびをしたりすることで開いて中耳の気圧を調整しています。
- 耳管開放症(じかんかいほうしょう): 耳管が開きっぱなしになることで、自分の声が響いて聞こえたり、耳のつまり感を感じたりすることがあります。加齢や体重減少が原因となることがあります。
- 滲出性中耳炎(しんしゅつせいちゅうじえん): 中耳に液体が溜まることで、耳のつまり感や聞こえにくさを感じることがあります。痛みや発熱を伴わないことが多いです。
- 航空性中耳炎: 飛行機に乗った際など、急激な気圧の変化によって、耳管の働きが追いつかなくなり、中耳の気圧調整がうまくいかなくなると、耳のつまり感や痛みを伴うことがあります。
3.内耳の異常による耳のつまり感:
- 低音障害型感音難聴(ていおんしょうがいがたかんおんなんちょう): 低い音の聞こえが悪くなる難聴で、耳のつまり感や、音が響いて聞こえたりする症状を伴うことがあります。
- メニエール病:めまいや難聴とともに、耳のつまり感を感じることがあります。
- 突発性難聴:ある日突然、片方の耳の聞こえが悪くなる病気で、耳のつまり感を伴うことがあります。
耳のつまり感の検査と診断
耳のつまり感の原因を特定するために、耳鼻咽喉科で以下の検査を行います。
- 問診:いつから症状が出始めたか、どのような時に症状がでやすいか、他の症状を伴うかなどを詳しくお聞きします。
- 耳鏡検査:耳の穴の中を観察し、外耳道や鼓膜に異常がないかを確認します。
- 聴力検査:音の聞こえを測定し、難聴の有無を確認します。
- ティンパノメトリー検査:鼓膜の動きや中耳の状態を調べます。
- 鼻腔内視鏡検査:必要に応じて、鼻の奥の状態を観察します。
- 画像検査:必要に応じて、CTやMRIなどの画像検査を行います。
耳のつまり感の治療法
耳のつまり感の治療は、原因によって異なります。
1.外耳の異常の場合
- 耳あか:耳鼻咽喉科で耳あかを除去してもらいます。
- 異物:耳鼻咽喉科で異物を除去してもらいます。
- 水:自然に乾燥するのを待ちますが、気になる場合は耳鼻咽喉科で相談してください。
- 外耳炎:炎症を抑える薬(点耳薬や塗り薬)を使用します。
- サーファーズイヤー:手術が必要になる場合があります。
2.中耳の異常の場合
- 耳管狭窄症:鼻の炎症を抑える薬や、鼻の通りをよくする薬を使用します。
- 耳管開放症:症状を緩和する薬を使用したり、耳管を閉じる手術を行う場合があります。
- 滲出性中耳炎:鼻の炎症を抑える薬や、中耳の液体を出すための処置を行うことがあります。
- 航空性中耳炎:鼻の通りをよくする薬を使用したり、耳抜きを促します。
3.内耳の異常の場合
- 低音障害型感音難聴:ステロイドなどの薬物療法を行います。
- メニエール病:めまいを抑える薬や、利尿薬などを使用します。
- 突発性難聴:ステロイドなどの薬物療法を行います。
まとめ
耳のつまり感は、さまざまな原因で起こりうる症状です。放置すると症状が悪化したり、日常生活に支障をきたす可能性もあります。そのため、耳のつまり感が続く場合は、自己判断せずに早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。
(お困りの際は、当院までご相談ください。適切な対応をさせていただきます。)