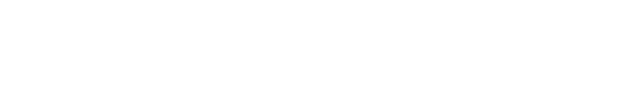聞こえが悪い
「最近、なんだか聞こえにくいな…」と感じることはありませんか? このように「聞こえにくい」という症状は、「難聴」とも呼ばれます。難聴には、生まれつき聞こえにくい場合から、徐々に聞こえが悪くなる場合、ある日突然聞こえなくなる場合まで、さまざまなタイプがあります。
難聴の種類と原因
難聴は、その起こり方や原因によって大きく分類できます。
1.先天性難聴
特徴:生まれつき、または出生後すぐに聞こえにくい状態。
原因:
- 遺伝的な要因:親から受け継いだ遺伝子によるもの。
- 妊娠中の感染症:風疹やおたふくかぜなど、妊娠中に母親が感染したことが原因の場合。
- 出産時のトラブル:難産や低酸素状態など。
2.後天性難聴
特徴:生まれてから、何らかの原因で聞こえが悪くなる状態。
- 加齢性難聴(老人性難聴): 年齢を重ねるごとに、徐々に両耳の聞こえが悪くなる状態。これは、内耳の機能が加齢とともに低下することによって起こります。誰でも年をとるにつれて経験する可能性のある変化です。
- 音響外傷:大きな音を長時間聴き続けることで、内耳の細胞がダメージを受け、難聴になる状態。コンサート会場や工事現場など、大きな音が発生する場所での作業や鑑賞には注意が必要です。
- 外傷性鼓膜穿孔:耳を叩かれたり、耳かきで誤って鼓膜を傷つけてしまうことで、鼓膜に穴が開き、聞こえが悪くなる状態。
- 薬剤性難聴:特定の薬の副作用によって、内耳がダメージを受け、難聴になる状態。抗生物質や利尿剤など、一部の薬は注意が必要です。
- 感染症による難聴:中耳炎や髄膜炎などの感染症が原因で、聞こえが悪くなることがあります。おたふくかぜ(ムンプス)も、稀に難聴を引き起こすことがあります。
- 突発性難聴:ある日突然、片方の耳の聞こえが著しく悪くなる状態。原因は不明なことが多いですが、ストレスやウイルス感染などが関与していると考えられています。
- メニエール病:内耳のリンパ液の異常によって起こる病気で、難聴、めまい、耳鳴りを伴います。
- 中耳炎:中耳に細菌やウイルスが感染し、炎症を起こした状態。炎症が内耳に波及すると難聴の原因になることがあります。
- 機能性難聴:原因となる病気がないにもかかわらず、心理的なストレスなどが原因で、聞こえが悪くなる状態。
難聴の症状
難聴の症状は、聞こえにくさの程度や、難聴の種類によって異なります。
- 全体的に音が小さく聞こえる:まるで耳栓をしているように、音が小さく聞こえる状態。
- 特定の音が聞こえにくい:高い音や低い音が聞こえにくいなど、特定の音域の音が聞こえにくい状態。
- 音が歪んで聞こえる:音が割れたり、ひずんで聞こえる状態。
- 会話が聞き取りにくい:特に騒がしい場所で、人の話が聞き取りにくい状態。
- 耳鳴り:キーンという音や、ジーという音が聞こえる。
- めまい:ふわふわするような、ぐるぐる回るようなめまいが起こる。
- 耳の痛み:耳の奥が痛む、耳だれが出る。
難聴を放置することの危険性
難聴を放置すると、日常生活に支障をきたすだけでなく、健康にもさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
- コミュニケーションの困難:会話が聞き取りにくくなり、友人や家族とのコミュニケーションが困難になる。
- 社会参加の低下:会議や集まりでの発言が減ったり、外出を控えるようになり、社会とのつながりが薄れる。
- 精神的な負担:聞こえないことへの不安やストレスから、うつ病や認知機能の低下につながるリスクがある。
- 認知症のリスク増加:最近の研究では、難聴は認知症の最大の危険因子の一つであることが指摘されています。難聴を放置すると、認知症の発症を早める可能性があります。
難聴の検査と診断
難聴の検査は、耳鼻咽喉科で行います。
主に下記のような検査が行われます。
- 問診:いつから聞こえにくくなったか、どのように聞こえにくいか、他の症状があるかなどを詳しく確認します。
- 耳鏡検査:耳の穴の奥(外耳道や鼓膜)を専用の器具で観察し、異常がないかを確認します。
- 聴力検査:音の聞こえの程度を測定する検査です。
- ティンパノメトリー検査:鼓膜の動きや、中耳の状態を調べる検査です。
- 語音聴力検査:言葉の聞き取り能力を調べる検査です。
- 画像検査:必要に応じて、CTやMRIなどの画像検査を行うことがあります。
これらの検査結果を総合的に判断して、難聴の種類や原因を特定します。
難聴の治療法
難聴の治療法は、原因によって異なります。
- 薬物療法:突発性難聴や中耳炎など、薬で治療できる難聴に対して、ステロイドや抗菌薬などが使用されます。
- 手術療法:中耳炎や鼓膜穿孔など、手術が必要な難聴に対して、鼓膜形成術や人工内耳手術などが行われます。
- 補聴器:加齢性難聴など、内耳の機能低下が原因の難聴に対して、音を増幅させる補聴器が有効です。補聴器は、聞こえの程度やライフスタイルに合わせて、適切なものを選ぶ必要があります。
- 人工内耳:重度の難聴に対して、手術によって内耳に電極を埋め込み、音を電気信号に変えて脳に伝える装置です。
補聴器について
補聴器は、聞こえを改善するための有効な手段です。しかし、補聴器は「聞こえを良くする」ものではなく、「聞こえを補う」ものです。そのため、補聴器を使うことで、必ずしも正常な聞こえが戻るわけではありません。補聴器は、専門家(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医など)の指導のもと、正しく調整して使用する必要があります。
まとめ
聞こえにくさは、放置すると生活の質を著しく低下させる可能性があります。「最近、聞こえにくいな…」と感じたら、まずは耳鼻咽喉科を受診し、専門医に相談しましょう。早期に適切な治療や補聴器の使用を開始することで、聞こえを改善し、より快適な生活を送ることができます。
(お困りの際は、当院までご相談ください。適切な対応をさせていただきます。)