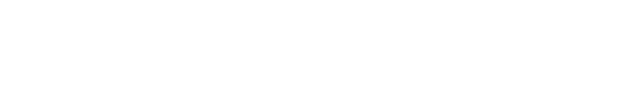肥厚性鼻炎
1.概要
肥厚性鼻炎(ひこうせいびえん)とは、鼻の粘膜や鼻甲介(びこうかい)と呼ばれる組織が慢性的な炎症によって厚く肥大し、鼻づまりや鼻みずなどの症状を引き起こす疾患です。特に下鼻甲介(かびこうかい)が肥厚することが多く、長期にわたる鼻づまりの原因となります。
2.症状
- 鼻づまり:粘膜の肥厚により鼻腔内が狭くなり、呼吸がしづらくなります。
- 鼻みず・後鼻漏(こうびろう):粘膜の慢性炎症によって粘り気のある鼻みずが多く出る場合や、のど側へ流れ落ちることがあります。
- 嗅覚低下:鼻づまりが続くと、においを感じにくくなることがあります。
- 頭痛・倦怠感:鼻閉感が長引くことで頭重感や集中力の低下を伴うことがあります。
3.原因
肥厚性鼻炎の主な要因は、鼻粘膜への慢性的な刺激や炎症です。
- 慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎:これらの疾患による粘膜の炎症が続くと、組織が肥厚しやすくなります。
- 点鼻薬(血管収縮薬):市販の点鼻薬の長期使用により反応性に肥厚が進む場合があります。
- 大気汚染・刺激物質:たばこや有害物質への長期的な曝露が粘膜を刺激します。
- 鼻づまりの放置:元々の鼻閉がある状態を放置し、鼻の炎症が長引くことで肥厚が進む場合があります。
- 自律神経の乱れ:ストレスや生活習慣の乱れによって鼻粘膜の血管が拡張しやすくなる場合もあります。
4.診断
- 問診・視診:鼻づまりの程度や鼻みずの性状、症状の継続期間などを確認します。
- 鼻内視鏡検査:鼻甲介や鼻腔内の状態を直接観察し、肥厚の度合いや炎症の範囲を詳しく確認します。
- 画像検査(CTなど):慢性副鼻腔炎の合併が疑われる場合などに行い、鼻や副鼻腔内の構造的異常や炎症の広がりを評価します。
- アレルギー検査:アレルギー性鼻炎が関係している可能性がある場合、血液検査や皮膚テストで原因アレルゲンを特定します。
5.治療
- 薬物療法:点鼻ステロイドや抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬などで粘膜の炎症を抑え、鼻づまりを改善させます。市販の点鼻薬の使用を控えるようにします。
- ネブライザー・鼻洗浄:鼻腔内の洗浄や吸入療法により、粘液の排出を促して炎症を抑えます。
- レーザー・高周波治療:鼻甲介粘膜を一部焼灼(しょうしゃく)し、肥厚を緩和する方法があります。
- 手術:重度の場合には、鼻甲介を切除・削減する手術を行うことがあります。手術後も適切なケアや通院が必要です。
- 生活改善:禁煙や規則正しい生活、ストレス管理などが再発予防に役立ちます。
肥厚性鼻炎は、放置していると鼻づまりなどの不快な症状が続くだけでなく、睡眠の質や生活の質を低下させる原因となります。気になる症状がある場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。