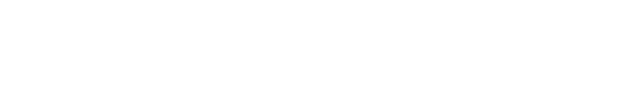1.概要
血管運動性鼻炎(けっかんうんどうせいびえん)とは、アレルギーや感染症による鼻炎ではなく、鼻粘膜の血管がさまざまな刺激(温度変化、湿度変化、ストレス、強いにおいなど)に対して過敏に反応することで生じる鼻炎です。鼻の粘膜を支配している自律神経のバランスが乱れることで、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの症状が引き起こされます。
2.症状
-
くしゃみ・鼻みず:透明でさらさらとした鼻みずが出やすく、とくに温度差が激しいときに起こりやすい
-
鼻づまり:鼻甲介(鼻腔内の構造)が腫れて気道を塞ぐため、呼吸がしづらくなる
-
目やのどのかゆみは少ない:アレルギー性鼻炎ほどかゆみを伴わないことが多い
-
発作的な症状:屋外から暖かい室内に入ったときなど、環境の急激な変化に伴い症状が強くなる場合があります
3.原因
-
自律神経の乱れ:交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、鼻粘膜の血管が過敏に反応する
-
温度差や湿度変化:寒暖差、乾燥、湿度の高さなどが誘因となりやすい
-
強いにおい・刺激物質:香水やタバコの煙、化学物質などに反応する場合
-
ストレスや疲労:精神的・身体的な負担が鼻粘膜の反応を増強させることがあります
アレルギー検査を行っても明確なアレルゲン(原因物質)が見つからないのが特徴です。
4.診断
-
問診・視診:症状の起こり方や季節性の有無、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎の可能性を除外します。
-
鼻腔内視鏡検査:鼻粘膜の状態や分泌物を観察し、他の疾患(鼻ポリープなど)を確認します。
-
アレルギー検査(血液・皮膚テスト):アレルギー反応を示す抗体の有無を調べ、アレルギー性鼻炎との鑑別に役立ちます。結果が陰性の場合は、血管運動性鼻炎が疑われます。
-
画像検査(CTなど):必要に応じて鼻腔や副鼻腔の構造的問題を確認し、他の疾患を除外します。
5.治療
-
生活習慣の改善:ストレスを減らし、十分な睡眠や休養をとること。また、急激な温度差を避ける工夫(マスクや衣類調整)を行います。
-
薬物療法:
-
点鼻ステロイド薬:鼻粘膜の炎症を抑え、血管の過剰反応を和らげます。
-
血管収縮薬(点鼻):一時的に鼻づまりを改善しますが、連用は避ける必要があります。
-
内服薬:抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬が有効な場合もあります。
-
手術療法:重症例では、鼻甲介粘膜を一部焼灼(しょうしゃく)するレーザー治療や下鼻甲介切除などを行うことがあります。
-
その他:鼻洗浄やネブライザーなどで鼻腔を清潔に保ち、粘膜の炎症を軽減する補助的治療も有効です。
血管運動性鼻炎は、完治が難しい場合もありますが、生活習慣の改善や薬物療法で症状をうまくコントロールできます。気になる症状がある方は、早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な治療方針を相談することが大切です。