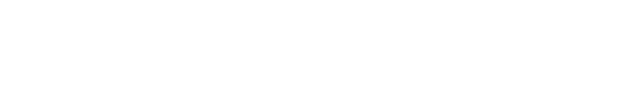難聴 (突発性難聴、加齢性難聴、騒音性難聴、音響外傷など)
1. 概要
難聴とは、音を聞き取る仕組み(聴覚経路)のどこかに障害が生じ、音が十分に脳まで伝わらなくなる状態を指します。人は音源から生じる空気の振動を耳で感じ取り、その振動を脳へ届けることで「音」として認識します。具体的には、音によって振動した鼓膜が小さな骨(耳小骨)を通して内耳に振動を伝え、内耳で電気信号に変換して聴神経を経由し脳へ送ります。難聴は、このプロセスのいずれかが障害されることで起こり、大きく分けて音の振動がうまく内耳まで伝わらない「伝音難聴」と、内耳や聴神経などの障害で振動が電気信号に変換されない、または脳へうまく伝わらない「感音難聴」があります。
2. 症状
- 周囲の声や音が聞き取りにくくなる
- テレビやラジオの音量を上げるようになる
- 会話の内容を繰り返し聞き直すことが増える
- 耳鳴りを伴うことがある
- 社会生活やコミュニケーションに支障をきたし、ストレスや孤立感につながる場合もある
症状は年齢や原因によってさまざまで、進行度や気づくタイミングも個人差があります。
3. 原因
- 伝音難聴:鼓膜に穴が開いている(鼓膜穿孔)、耳小骨の欠損・奇形、中耳炎などにより、音の振動が内耳へ十分に伝わらずに起こります。
- 感音難聴:内耳が障害されて振動を電気信号に変換できない場合や、聴神経の障害で信号が脳に伝わりにくい場合に発生します。突発性難聴、内耳炎、加齢性難聴、聴神経腫瘍などが代表的な原因です。
これらの原因によって、音を脳に届けるプロセスが妨げられ、難聴が起こります。
4. 診断
- 問診・視診:耳の構造に異常がないか、病歴・生活習慣などを確認します。
- 聴力検査:純音聴力検査や語音聴力検査で、聴こえの程度や音域ごとの聞こえ方を調べます。
- インピーダンス・ティンパノメトリー:中耳の状態や鼓膜の動きを測定します。
- 画像検査(CT・MRIなど):必要に応じて、耳小骨や内耳、聴神経の状態を確認します。
これらの結果に基づき、伝音難聴か感音難聴か、あるいは混合性難聴(両方の要素がある状態)かを判断し、原因疾患を特定します。
5. 治療
- 薬物療法突発性難聴などで早期に治療を行う場合に有効とされるステロイド療法や、血流改善薬などが用いられます。
- 手術療法:鼓膜穿孔を修復する鼓膜形成術、中耳炎の手術、耳小骨の再建などが挙げられます。また、聴神経腫瘍の場合は外科的な治療が必要となる場合もあります。
- 補聴器や人工内耳:聴力が戻らない場合でも、補聴器や人工内耳(人工内耳埋め込み手術)によって聞こえを補う方法があります。
- リハビリテーション:聞こえのトレーニングやコミュニケーションの方法を学ぶことで、生活の質を向上させます。
難聴は原因によって治療法やリハビリテーションの進め方が異なります。気になる症状があれば、早めに耳鼻咽喉科を受診し、正確な診断と適切な治療を受けることが大切です。