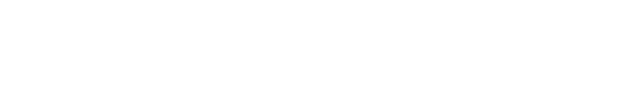顔が曲がる・顔が動きにくい
「片方の顔が動きにくい」「口角が下がって顔が曲がっているように見える」「まぶたが閉じにくい」など、顔の動きに異常を感じたら、それは顔面神経麻痺(がんめんしんけいまひ)の可能性があります。顔面神経麻痺は、日常生活に支障をきたすだけでなく、見た目の変化から精神的なストレスを感じることもあります。ここでは、顔面神経麻痺の原因や対処法について詳しく解説します。
顔面神経とは?
顔面神経とは、顔の表情を作る筋肉を動かす神経のことです。顔面神経は、脳から出て、耳の奥を通って顔の筋肉に繋がっています。顔面神経は、表情筋を動かすだけでなく、涙や唾液の分泌、味覚、聴覚にも関わっています。
顔面神経麻痺とは?
顔面神経麻痺とは、この顔面神経の働きが障害され、顔の筋肉が麻痺することで、顔の動きに異常が現れる状態を指します。
顔面神経麻痺の種類
顔面神経麻痺には、大きく分けて以下の2つの種類があります。
1.末梢性顔面神経麻痺(まっしょうせい がんめんしんけいまひ)
特徴: 顔面神経が脳から出てから、顔の筋肉に繋がるまでの間に障害される状態。
原因: ウイルス感染、外傷、腫瘍など様々な原因が考えられます。
- 代表的な病気:
- ベル麻痺:明確な原因がなく、顔面神経麻痺のみが生じる病気。単純ヘルペスウイルスの再活性化が関与していると考えられています。
- ハント症候群:水痘・帯状疱疹ウイルスが原因で、顔面神経麻痺と同時に、耳の周りに水疱(帯状疱疹)ができる病気。めまい、難聴、耳鳴りなどを伴うことがあります。
2.中枢性顔面神経麻痺(ちゅうすうせい がんめんしんけいまひ)
特徴: 脳の中の顔面神経を司る部分が障害される状態。
原因: 脳梗塞、脳出血、脳腫瘍などの脳の病気が原因で起こることがあります。
- 補足: 中枢性顔面神経麻痺では、額のしわ寄せが残ることが多いとされています。
顔面神経麻痺の症状
顔面神経麻痺の症状は、障害される場所や程度によって様々ですが、主な症状として以下のようなものがあります。
- 顔の麻痺:
- 顔の片側が動きにくい、または動かせない。
- 口角が下がる、口が歪む。
- まぶたが閉じにくい、または完全に閉じない。
- 額にしわを寄せることができない。
- 眉を上げることができない。
- 鼻を動かすことができない。
- その他の症状:
- 味覚障害:味を感じにくくなる、味がわからなくなる。
- 涙や唾液の分泌異常:涙が出にくい、唾液が出にくい、または過剰に出る。
- 聴覚過敏:音が響いて聞こえる、音が大きく聞こえる。
- 耳鳴り:耳鳴りが起こることがある。
- めまい:めまいを感じることがある。
- 耳の痛み:耳の奥が痛むことがある。
顔面神経麻痺を引き起こす主な病気
顔面神経麻痺を引き起こす主な病気としては、以下のものが挙げられます。
1.末梢性顔面神経麻痺
- ベル麻痺: 最も多い原因で、顔面神経麻痺のみが生じます。
- ハント症候群: 帯状疱疹ウイルスによる感染症で、顔面神経麻痺の他に、耳の周りの水疱、めまい、難聴などを伴います。
- 外傷: 顔面を強く打ったり、顔面の手術などが原因で、顔面神経が損傷することがあります。
- 中耳炎: 中耳炎が悪化し、顔面神経に炎症が及ぶことがあります。
- 腫瘍: 耳の奥や脳にできた腫瘍が、顔面神経を圧迫し、麻痺を引き起こすことがあります。
- その他: まれに、糖尿病や妊娠などが原因で、顔面神経麻痺が起こることがあります。
2.中枢性顔面神経麻痺
- 脳梗塞・脳出血: 脳の血管が詰まったり破れたりして、脳の一部が損傷することで、顔面神経麻痺が起こることがあります。
- 脳腫瘍: 脳にできた腫瘍が顔面神経を圧迫し、麻痺を引き起こすことがあります。
- 脳炎・髄膜炎: 脳や脊髄を覆う膜に炎症が起こり、顔面神経麻痺を起こすことがあります。
顔面神経麻痺の検査と診断
顔面神経麻痺の原因を特定するために、耳鼻咽喉科や神経内科では、以下のような検査を行います。
- 問診: いつから症状が出始めたか、どのような症状があるか、他に病気を持っているかなどを詳しくお聞きします。
- 顔面神経機能検査:顔の筋肉の動きや、神経の電気的な反応を調べます。
- 聴力検査:耳の聞こえ具合を調べます。
- めまい検査:めまいの有無や原因を調べます。
- 血液検査:ウイルス感染の有無や、炎症の程度などを調べます。
- 画像検査:必要に応じて、顔面や脳のCT検査やMRI検査を行い、腫瘍などの異常がないかを確認します。
- 髄液検査: 必要に応じて、脳脊髄液を採取し、炎症の有無などを調べます。
顔面神経麻痺の治療法
顔面神経麻痺の治療法は、原因や重症度によって異なります。
1.ベル麻痺の場合
- ステロイド薬:炎症を抑え、神経の回復を促すために、ステロイド薬を使用します。
- 抗ウイルス薬:ウイルス感染が疑われる場合、抗ウイルス薬を使用することがあります。
- ビタミン剤:神経の回復を助けるために、ビタミン剤を服用することがあります。
- リハビリテーション:顔の筋肉を動かす訓練や、マッサージなどを行います。
2.ハント症候群の場合
- 抗ウイルス薬:ウイルスの増殖を抑えるために、抗ウイルス薬を使用します。
- ステロイド薬:炎症を抑え、神経の回復を促すために、ステロイド薬を使用します。
- 鎮痛薬:痛みや発熱を抑えるために、鎮痛薬を使用することがあります。
3.中枢性顔面神経麻痺の場合
- 原因となっている脳の病気に対する治療を行います。
4.共通の治療法
- 眼の保護:まぶたが閉じにくい場合は、眼の乾燥を防ぐために、眼薬や保護用のテープなどを使用します。
- リハビリテーション:顔の筋肉を動かす訓練や、マッサージなどを行います。
リハビリテーション
顔面神経麻痺のリハビリテーションは、麻痺した筋肉の回復を促し、顔の左右差を少なくするために行います。具体的には、以下のような内容を行います。
- 顔面筋トレーニング:顔の筋肉を動かす体操や、表情を作る練習を行います。
- マッサージ:顔の筋肉をマッサージすることで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。
- 温熱療法:顔を温めることで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。
日常生活での注意点
- 目を保護する:まぶたが閉じにくい場合は、眼の乾燥を防ぐために、眼薬を使い、寝る時には眼を保護するための眼帯を着用しましょう。
- 顔を温める:顔を温めることで、血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。
- 無理をしない:症状が強い時は、無理をせず安静に過ごしましょう。
まとめ
「顔が曲がる」という症状は、顔面神経麻痺の可能性があります。放置すると症状が固定化したり、後遺症が残る可能性もあります。顔面神経麻痺が疑われる場合は、自己判断せずに早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。発症後の1週間が勝負です。早期に治療を開始することで、症状の改善を促し、後遺症のリスクを減らすことができます。
(お困りの際は、当院までご相談ください。適切な対応をさせていただきます。)