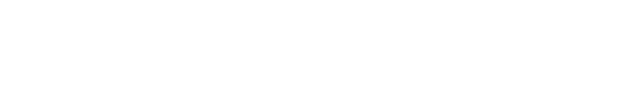飲み込めない・むせる
「食べ物がのどにつかえる感じがする」「飲み込むときにむせてしまう」といった症状で悩んでいませんか? 食べ物や飲み物をスムーズに飲み込むことは、私たちの健康を維持する上で非常に重要です。ここでは、「飲み込めない」「むせる」といった症状の原因や、対処法について詳しく解説します。
食べ物や飲み物が飲み込まれる仕組み
食べ物や飲み物は、口から入った後、以下の経路を通って胃に送り込まれます。
- 咀嚼(そしゃく):食べ物を口の中で噛み砕き、唾液と混ぜて飲み込みやすい状態にします。
- 嚥下(えんげ):舌やのどの筋肉を使い、食べ物をのどの奥(咽頭)へと送り込みます。
- 食道への移動:咽頭を通った食べ物は、食道を通って胃へと運ばれます。
- 補足:飲み込む際には、気管(肺への空気の通り道)に食べ物や飲み物が入らないように、喉頭蓋(こうとうがい)という蓋が気管を塞ぐ仕組みが働いています。
飲み込めない(嚥下困難:えんげこんなん)とは?
飲み込めない(嚥下困難)とは、食べ物や飲み物が口から胃に送り込まれる過程で、どこかに障害が起こり、スムーズに飲み込むことができない状態を指します。
飲み込めない原因
飲み込めない原因は様々ですが、主なものとして以下のようなものがあげられます。
1.通路の狭窄(きょうさく)
- 腫瘍(しゅよう):咽頭がんや食道がんなどの悪性腫瘍が、のどや食道の通り道を狭めてしまい、飲み込みを困難にする場合があります。
- 補足:特に悪性腫瘍は、早期発見・早期治療が重要です。
- 炎症:咽頭炎や食道炎などの炎症によって、のどの粘膜が腫れ、飲み込みを困難にする場合があります。
- 食道狭窄(しょくどうきょうさく):食道の炎症や手術後、先天的な異常などによって食道が狭くなり、食べ物が通りにくくなる状態。
2.筋肉や神経の機能低下
- 脳卒中(脳梗塞、脳出血):脳卒中によって、飲み込みに関わる筋肉や神経の機能が低下し、飲み込みが難しくなることがあります。
- 神経系の病気:パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経系の病気によって、飲み込みに関わる筋肉の動きが悪くなり、飲み込みが難しくなることがあります。
- 筋疾患:筋ジストロフィーなどの筋肉の病気によって、飲み込む力が弱くなることがあります。
- 加齢:加齢に伴い、飲み込むための筋肉が衰え、飲み込みが難しくなることがあります(嚥下機能低下)。
3.その他
- 食道運動機能障害:食道の蠕動運動(ぜんどううんどう:食べ物を送り出すための筋肉の動き)がうまく働かないと、食べ物が食道に詰まりやすくなり、飲み込みにくさを感じることがあります。
- 精神的な原因:ストレスや不安などの精神的な要因によって、のどの筋肉が緊張し、飲み込みにくさを感じることがあります。
- 薬の副作用:一部の薬の副作用で、のどの筋肉の動きが悪くなり、飲み込みにくさを感じることがあります。
- 異物:魚の骨などがのどに引っかかると、飲み込みにくさを感じることがあります。
むせる(誤嚥:ごえん)とは?
むせる(誤嚥)とは、本来は食道に入るはずの食べ物や飲み物が、誤って気管に入ってしまう状態を指します。気管に入った異物に対して、咳反射が起こるため、むせることがあります。
むせる原因
むせる原因は様々ですが、主なものとして以下のようなものがあげられます。
1.飲み込む機能の低下
- 高齢による嚥下機能の低下。
- 脳卒中や神経系の病気による、飲み込む筋肉や神経の機能低下。
- 口の筋肉の衰え
2.喉頭の機能低下
- 喉頭蓋の動きが悪く、気管への蓋が十分にできない状態。
- 声帯の動きが麻痺したり、うまく閉じない状態。
3.その他
- 食べ物や飲み物の形状の問題(大きすぎる、乾燥している、など)
- 食べる姿勢が悪い
- 食事中に会話が多い
- 意識が低下している状態
飲み込めない・むせる場合の検査と診断
飲み込めない、むせる症状の原因を特定するために、耳鼻咽喉科や内科、リハビリテーション科などで以下のような検査を行います。
- 問診:いつから症状が出始めたか、どのような時に症状が出やすいか、他の症状を伴うかなどを詳しくお聞きします。
- 嚥下内視鏡検査(VE):鼻から内視鏡を挿入し、のどの状態や、食べ物や飲み物を飲み込む様子を観察します。
- 嚥下造影検査(VF):飲み込む様子をX線で撮影する検査。食べ物や飲み物がどこを通っているか、誤嚥の有無を確認します。
- 嚥下機能評価:口や舌の動き、飲み込む筋肉の力などを評価します。
- 喉頭内視鏡検査:喉頭や声帯の状態を観察します。
- 画像検査:必要に応じて、首や胸部のレントゲン検査やCT検査を行い、腫瘍や構造的な異常がないかを確認します。
- 神経学的検査:神経系の病気が疑われる場合は、神経学的検査を行います。
- 血液検査:炎症の程度や、貧血の有無などを調べます。
飲み込めない・むせる場合の治療法
飲み込めない、むせる症状の治療法は、原因によって異なります。
1.通路の狭窄が原因の場合
- 腫瘍:手術や放射線治療、化学療法などを行います。
- 炎症:炎症を抑える薬を使用します。
- 食道狭窄:食道拡張術や手術を行うことがあります。
2.筋肉や神経の機能低下が原因の場合
- リハビリテーション:言語聴覚士や理学療法士によるリハビリテーションで、飲み込むための筋肉を鍛えたり、飲み込み方を練習します。
- 薬物療法:神経系の病気に対する薬を使用することがあります。
3.その他が原因の場合
- 食道運動機能障害:食道の蠕動運動を改善する薬を使用することがあります。
- 精神的な原因:ストレスを軽減する薬やカウンセリングなどを行います。
- 薬の副作用:医師に相談し、薬の調整や変更を検討します。
4.共通の治療法
- 食事の工夫:食べやすいように、食事の形状や硬さを調整します。とろみ剤を利用するのも有効です。
- 姿勢の調整:食事をする時の姿勢を調整します(少し顎を引いた状態が推奨されます)。
- 口腔ケア:口の中を清潔に保ち、細菌の繁殖を抑えます。
- 誤嚥性肺炎の予防:誤嚥によって肺炎を起こしてしまう場合は、抗菌薬などを使用します。
日常生活での注意点
- ゆっくりと食事をする:ゆっくりとよく噛んで、一口ずつ飲み込むようにしましょう。
- 食事の環境を整える:静かで落ち着いた場所で食事をしましょう。
- 食事の姿勢を意識する:少し顎を引いた姿勢で食事をしましょう。
- 食べやすい食事にする:水分にとろみをつけたり、食材を細かく刻むなど、食べやすいように工夫しましょう。
- 適度な運動を行う:適度な運動は、全身の筋肉を維持するのに役立ちます。
- 口や舌の体操をする:口や舌の筋肉を鍛える体操をしましょう。
- 口腔ケアをする:食事の後に歯を磨き、口腔内を清潔に保ちましょう。
まとめ
「飲み込めない」「むせる」という症状は、放置すると重篤な肺炎につながることもあります。もっとも注意する必要があるのは腫瘍、なかでも悪性腫瘍により通り道が狭くなる状態なので、咽頭がん、食道がんなどの有無をしっかり確認する必要があります。高齢者で飲み込みの機能が低下し、誤嚥を繰り返すと重篤な肺炎になることもあります。症状が続く場合は、自己判断せずに早めに耳鼻咽喉科や内科を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。
(お困りの際は、当院までご相談ください。適切な対応をさせていただきます。)