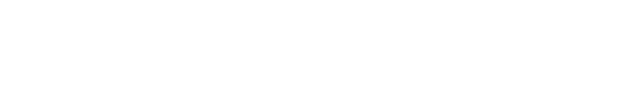鼻水が出る
「鼻水が止まらない」「いつも鼻をかんでいる」という経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。鼻水は、私たちの体を守るために必要な生理現象ですが、その量や状態によっては、何らかの病気のサインであることもあります。
鼻水の種類と特徴
鼻水は、その性状によって大きく2つの種類に分けられます。
1.膿性鼻漏(のうせいびろう)
特徴:ドロドロとした粘り気のある、黄色や緑色の鼻水。
原因:細菌感染や炎症によって、鼻の奥の副鼻腔に膿が溜まることが原因で起こります。
- 補足:いわゆる「蓄膿症」と呼ばれる副鼻腔炎でよく見られます。
2.水様性鼻漏(すいようせいびろう)
特徴:水のようにサラサラとした透明な鼻水。
原因:鼻の粘膜の炎症や刺激によって、鼻水が過剰に分泌されることが原因で起こります。
- 補足:風邪やアレルギー性鼻炎の際に多く見られます。
鼻水が出る原因
鼻水が出る原因は多岐にわたりますが、主な原因として以下のものがあげられます。
1.感染症による鼻水
- 風邪(急性鼻炎): ウイルス感染によって鼻の粘膜が炎症を起こし、水様性鼻漏が出ます。咳やのどの痛み、発熱などの症状を伴うことが多いです。
- 副鼻腔炎(蓄膿症): 細菌やウイルスが副鼻腔(鼻の奥にある空洞)に感染し、炎症を起こすと、膿性鼻漏が出ます。顔面痛や頭痛を伴うこともあります。
- 乳幼児の鼻への異物:乳幼児が鼻に異物(おもちゃや食べ物など)を入れてしまうと、細菌感染を起こし、膿性鼻漏が続くことがあります。
2.鼻の構造的な異常による鼻づまり
- アレルギー性鼻炎:花粉やハウスダストなどのアレルギー物質に反応して、鼻の粘膜が炎症を起こし、水様性鼻漏が出ます。くしゃみや鼻づまりを伴うことが多いです。
3.自律神経の乱れによる鼻水
- 血管運動性鼻炎: 自律神経のバランスが乱れることで、鼻の粘膜の血管が過剰に反応し、水様性鼻漏が出ます。温度変化やストレスなどが誘因となることがあります。アレルギー性鼻炎に似た症状が出ますが、アレルギー反応は伴いません。
4.その他の原因
- 寒暖差:急激な温度変化によって、鼻の粘膜が刺激され、鼻水が出ることがあります。
- 刺激物:タバコの煙や香水などの刺激物が、鼻の粘膜を刺激して鼻水が出ることがあります。
- 血管運動性鼻炎:自律神経のバランスが乱れることで、鼻の粘膜の血管が過剰に反応し、鼻水が出ることがあります。
- 妊娠:妊娠中はホルモンバランスが変化し、鼻の粘膜が敏感になるため、鼻水が出やすくなることがあります。
- 鼻腔乾燥:鼻の粘膜が乾燥すると、保護するために鼻水が分泌されることがあります。
鼻水の検査と診断
鼻水の原因を特定するために、耳鼻咽喉科では以下の検査を行います。
- 問診:鼻水の種類、色、量、いつから症状が出始めたか、他の症状を伴うかなどを詳しくお聞きします。
- 鼻鏡検査:鼻の穴の中を観察し、鼻の粘膜の状態や鼻水の性状などを確認します。
- 鼻腔通気度検査:鼻の通気具合を測定する検査です。
- 鼻汁培養検査:鼻水の中に細菌や真菌がいるかを調べる検査です。
- アレルギー検査:アレルギー性鼻炎が疑われる場合は、血液検査や皮膚検査などを行います。
- CT検査:副鼻腔炎が疑われる場合は、CT検査を行うことがあります。
鼻水の治療法
鼻水の治療は、原因によって異なります。
1.感染症による鼻水の場合
- 風邪:十分な休息と水分補給を心がけ、必要に応じて解熱鎮痛薬や咳止めなどの対症療法を行います。
- 副鼻腔炎:抗菌薬や粘液溶解薬を使用し、炎症を抑えます。
- 乳幼児の鼻への異物:耳鼻咽喉科で異物を除去します。
2.アレルギーによる鼻水の場合
- 抗アレルギー薬:アレルギー反応を抑える薬を内服します。
- ステロイド点鼻薬:鼻の粘膜の炎症を抑える点鼻薬を使用します。
- アレルギーの原因物質を避ける:花粉やハウスダストなどのアレルギーの原因物質をできるだけ避けるようにしましょう。
3.自律神経の乱れによる鼻水の場合
- 抗コリン薬:鼻水の分泌を抑える薬を内服します。
- 生活習慣の改善:ストレスを避け、規則正しい生活を心がけましょう。
4.共通の治療法
- 鼻洗浄: 生理食塩水などで鼻を洗浄し、鼻の中を清潔に保ちます。
- ネブライザー療法: 薬液を霧状にして鼻やのどに吸入させ、炎症を抑えます。
- 加湿: 部屋の湿度を適切に保ち、鼻の粘膜が乾燥するのを防ぎます。
まとめ
鼻水は、誰にでも起こりうる症状ですが、原因によって治療法は異なります。鼻水が続く場合は、自己判断せずに早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。
(お困りの際は、当院までご相談ください。適切な対応をさせていただきます。)